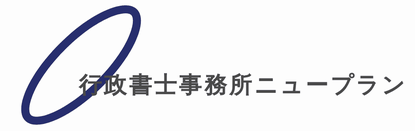貨物利用運送事業(通称「水屋」と呼ばれます)とは、自社での運送は行わず、実際の運送はすべて外注の実運送事業者(庸車・下請け)を利用して行う貨物の運送のことをいいます。
貨物利用運送事業には、第一種貨物利用運送事業と第二種貨物利用運送事業の2種類があります。
- 第一種貨物利用運送事業:実運送事業者の行う運送において、トラック・船舶・航空・鉄道のうち1種類のみを利用して行うもの
- 第二種貨物利用運送事業:船舶・航空・鉄道による運送と、その前後のトラックによる集荷・配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するもの
第一種貨物利用運送事業を行うには国土交通大臣の登録を受けなければなりません。運輸局における標準処理期間は2~3ヶ月と長期間に渡りますので、計画的に準備を進める必要があります。
第一種貨物利用運送事業の登録を受けることで、トラック・トレーラーを所有せずに運送業を開業することが可能になります。
また、オフィス移転や引越しの利用運送を行う場合にも、この第一種貨物利用運送事業の登録が必要となります。
行政書士事務所ニュープランでは、第一種貨物利用運送事業の登録申請・許可取得代行サービスを行っております。
また、輸送モードが貨物自動車(トラック・トレーラー等)の場合のみでなく、船舶(内航・外航)の場合の登録申請も代行しております。ぜひ、運輸専門の行政書士にご依頼ください。
第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービス

当事務所では、第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得を代行いたします。
行政書士への報酬額はリーズナブルな価格設定により、貨物自動車¥100,000(税込¥110,000)、内航・外航・鉄道¥130,000(税込¥143,000)で承ります。
利用運送事業の免許を取得されたい方は、法人・個人事業主を問わず、ぜひ行政書士事務所ニュープランにご依頼ください。
千葉県・東京都・埼玉県・神奈川県・茨城県・栃木県・群馬県・山梨県、他 全国対応
第一種貨物利用運送事業登録申請代行の動画解説
第一種貨物利用運送事業登録の要件
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるためには、大きく分けて「人」「物」「金」の3つの用件を満たす必要があります。
- 「人」の要件
- 「物」の要件
- 「金」の要件
利用運送の要件を満たすかどうか、専門の行政書士が無料診断いたします。
「人」の要件
欠格事由
第一種貨物利用運送事業登録の申請者(個人事業の場合は個人事業主、法人の場合は法人と役員全員)は、以下の欠格事由に該当すると貨物利用運送事業の登録を受けることができません(貨物利用運送事業法第6条)。
・1年以上の懲役または禁固の刑に処せられ、その執行を終えた日から2年を経過しない者
・第一種貨物利用運送事業の登録または第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
・申請前2年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
「物」の要件
営業所
第一種貨物利用運送事業の営業所として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 使用権原を有すること。
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
都市計画法における以下の区域においては、原則的に第一種貨物利用運送事業の営業所として使用することはできません。
- 市街化調整区域
- 第一種低層住居専用地域
- 第二種低層住居専用地域
- 第一種中高層住居専用地域
- 第二種中高層住居専用地域(一定条件の場合)
- 第一種住居地域(一定条件の場合)
また、建築基準法上の建築物とは、「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの」と定められており、プレハブ・ユニットハウス・コンテナハウス等も建築基準法上の建築物に当たるため建築基準法の適用の範疇に入り、そのままでは運送業の営業所として使用することはできません。
そのような場合には、原則基礎工事・建築確認申請をする必要があります。
また、不動産登記法上の地目が農地(田・畑)の場合には、農地法に基づき農地転用の手続きをしなければ第一種貨物利用運送事業の営業所として使用することはできません。
使用権原を有すること。
営業所が自己所有であるか賃貸している必要があります。
営業所の使用権限は宣誓書により自認します。土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)や賃貸借契約書は必要ありません。
保管施設(必要とする場合)
第一種貨物利用運送事業の保管施設として使用するためには、以下の要件を満たさなければなりません。
- 都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
- 使用権原を有すること。
- 規模・構造および設備が適切なものであること。
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであること。
都市計画法、建築基準法、消防法、農地法等関係法令に抵触しないものであることが必要です。
使用権原を有すること。
保管施設が自己所有であるか賃貸している必要があります。
保管施設の使用権限は宣誓書により自認します。土地建物の登記簿謄本(登記事項証明書)や賃貸借契約書は必要ありません。
規模・構造および設備が適切なものであること。
保管施設は、利用運送を遂行するために必要な保管能力を有し、盗難等に対する適切な予防方法を講じている必要があります。
「金」の要件
財産的基礎
第一種貨物利用運送事業の登録を受けるには、純資産300万円以上を所有している必要があります。
資本金のことではありません。貸借対照表の右下にある「純資産合計」が300万円以上である必要があります。
個人事業主の場合は、純資産は「資産-負債」で計算されます。住宅ローンがある場合は負債が大きくなりますので注意しましょう。

一般貨物自動車運送事業者が他の事業者に庸車を行う場合、利用運送の追加認可が必要になります。
利用運送追加認可を受ける手続きはこちら。
貨物利用運送事業を始めるメリット
貨物利用運送事業は、運送業であるにもかかわらずトラック等のハード面を所有する必要がなく、一般貨物自動車運送事業に比べると準備も容易なため、登録・許可の完了までの期間が短く済みます。
また、トラック等のハード面を所有する必要がなく、運行管理者・整備管理者・ドライバー等の人員も雇用する必要がないということは、それだけ経営コストが少なくて済むということになります。
このように貨物利用運送事業は経営リスクが非常に少ない事業であると言えます。
第一種貨物利用運送事業の運送委託契約書
運輸局に対して利用運送事業の登録申請を行う際に、実運送事業者との運送委託契約書を提出する必要があります。
利用運送事業の運送委託契約書は、印紙税法に定める第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)に該当し、印紙代は一律4,000円となっています。
印紙上に会社実印で割印をします。
利用運送事業の運送委託契約書の内容は、本当に利用運送事業に該当するかどうかなど運輸局によって厳しく審査されますので、事前に行政書士にご相談下さい。
第一種貨物利用運送事業登録申請の標準審査期間
第一種貨物利用運送事業登録申請の標準審査期間(登録完了までの月数)は3か月です。
第一種貨物利用運送事業の罰則
第一種貨物利用運送事業を営むためには登録を受けることが必要であり、登録を受けずに第一種貨物利用運送事業を営んだ場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください(貨物利用運送事業法第62条第1項第1号)。
第一種貨物利用運送事業登録・許可取得代行サービスの流れ
当事務所における第一種貨物利用運送事業登録代行サービスの流れは以下のようになります。
- ご相談まずは当事業所へお電話またはメールにてお問い合わせください。
- 正式なご依頼・ご入金正式なご依頼の後、指定の銀行口座に料金をお振込みください。
- 基本事項の確認基本事項の確認のため、ヒアリングシートを用いて主に「人」「物」「金」の3つの条件についてお伺いいたします。
- 必要書類のご準備お客様にご用意いただく必要書類のご案内をさせて頂きます。
お客さまにお渡しした必要書類のリストをもとに、必要書類のご準備をお願い致します。 - 不動産調査(保管施設ありの場合)お客様の営業所にお伺いして、保管施設の調査を行います。
利用運送の保管施設に関しては、運送途中の経過地として積替えに使用する場合のみ登録が必要になります。したがって、保管施設が出発地や目的地となる場合は、登録は必要ありません。
その際、今後の手続きの流れについてのご説明を行います。 - 申請書類の作成当事務所にて第一種貨物利用運送事業登録の申請書類を作成致します。
押印が必要な書類はお客様に送付し、押印して頂きます。 - 運輸支局への申請書類の提出管轄の運輸支局へ第一種貨物利用運送事業登録の申請書類を提出致します。
- 登録通知書の交付申請から約2~3ヶ月後に登録通知書が交付されます。
- 登録免許税の納付登録免許税9万円を金融機関で納付致します。
- 運賃料金設定届の提出運賃料金を設定した後、管轄の運輸支局へ運賃料金設定届を提出致します。
第一種貨物利用運送事業登録申請・許可取得代行サービスに関するQ&A
- 利用運送業の登録にかかる期間はどれくらいですか?
-
利用運送業の登録の標準審査期間は2~3か月となっています。
現在、実際には3か月の期間がかかっています。営業所が都市計画法等の関係法令に抵触しないことの確認はしてもらえますか?はい、ご相談の段階で、事前に確認をとることは可能です。
その場合には、料金はかかりません。資本金が300万円あれば、登録可能でしょうか?貸借対照表上の純資産の合計が300万円以上あることが必要です。
資本金が300万円あっても条件を満たすとは限りません。
管轄運輸局・運輸支局
【審査機関】
関東運輸局 自動車交通部貨物課
〒231-8433 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL:045-211-7248

【申請受付機関】
千葉運輸支局 輸送担当
〒261-0002 千葉県千葉市美浜区新港198番地
TEL:043-242-7336

【申請受付機関】
東京運輸支局 輸送担当
〒140-0011 東京都品川区東大井1丁目12番17号
TEL:03-3458-9231

【申請受付機関】
埼玉運輸支局 輸送担当
〒331-0077 埼玉県さいたま市西区大字中釘2154-2
TEL:048-624-1835

【申請受付機関】
神奈川運輸支局 輸送担当
〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町3540番地
TEL:045-939-6800

【申請受付機関】
茨城運輸支局 輸送担当
〒310-0844 茨城県水戸市住吉町353番地
TEL:029-247-5348

【申請受付機関】
栃木運輸支局 輸送担当
〒321-0169 宇都宮市八千代1丁目14番8号
TEL:028-658-7011

【申請受付機関】
群馬運輸支局 輸送担当
〒371-0007 群馬県前橋市上泉町399番地の1
TEL:027-263-4440

【申請受付機関】
山梨運輸支局 輸送担当
〒406-0034 山梨県笛吹市石和町唐柏1000の9
TEL:055-261-0880

地域別詳細
全国対応いたします。
千葉県 【全域】
浦安市 市川市 船橋市 習志野市 鎌ヶ谷市 八千代市 白井市 印西市 千葉市 四街道市 佐倉市 成田市 香取市 八街市 市原市 袖ヶ浦市 木更津市 君津市 松戸市 柏市 流山市 我孫子市 野田市
東京都 【全域】
江戸川区 江東区 葛飾区 墨田区 中央区 千代田区 台東区 荒川区 文京区 足立区 北区 豊島区 新宿区 渋谷区 港区 中野区 目黒区 品川区 板橋区 練馬区 杉並区 世田谷区 大田区 八王子市 町田市 府中市 調布市 西東京市 小平市 三鷹市 日野市 立川市 東村山市 多摩市 青梅市 武蔵野市 国分寺市 小金井市 東久留米市 昭島市 稲城市 東大和市 あきる野市 狛江市 国立市 清瀬市 武蔵村山市 福生市 羽村市
茨城県 【全域】
水戸市 つくば市 日立市 ひたちなか市 土浦市 古河市 取手市 筑西市 神栖市 牛久市 龍ケ崎市 石岡市 笠間市 鹿嶋市 常総市 守谷市 常陸太田市 坂東市 那珂市 結城市 小美玉市 鉾田市 北茨城市 稲敷市 桜川市 常陸大宮市 下妻市 つくばみらい市 かすみがうら市
埼玉県 【全域】
さいたま市 川口市 川越市 所沢市 越谷市 草加市 春日部市 上尾市 熊谷市 新座市 狭山市 久喜市 入間市 深谷市 三郷市 朝霞市 戸田市 鴻巣市 加須市 富士見市 ふじみ野市 坂戸市 東松山市 行田市 飯能市 八潮市 本庄市 和光市 桶川市 蕨市 鶴ヶ島市 志木市 北本市 秩父市 吉川市 蓮田市
神奈川県 【全域】
横浜市 川崎市 相模原市 横須賀市 藤沢市 平塚市 茅ヶ崎市 大和市 厚木市 小田原市 鎌倉市 秦野市
栃木県 群馬県 山梨県 宮城県 福島県 山形県 秋田県 岩手県 青森県 新潟県 長野県 富山県 石川県 大阪府 京都府 兵庫県